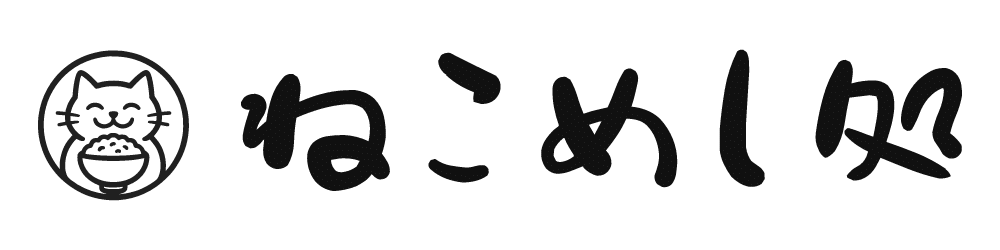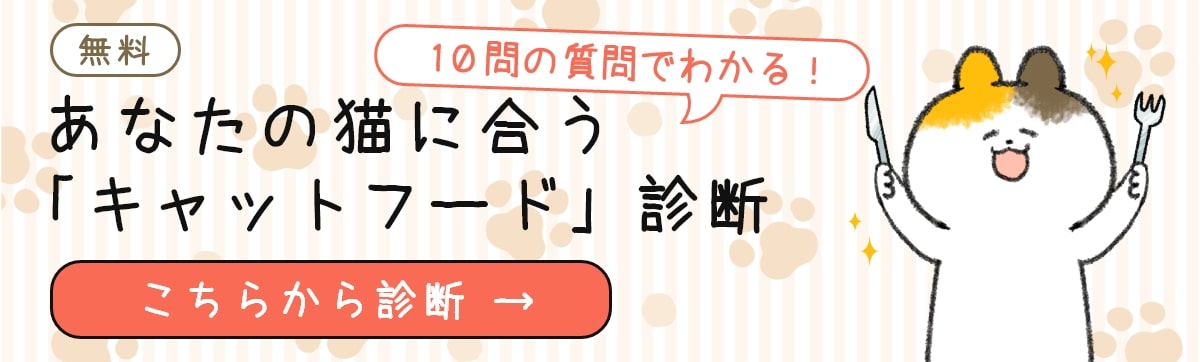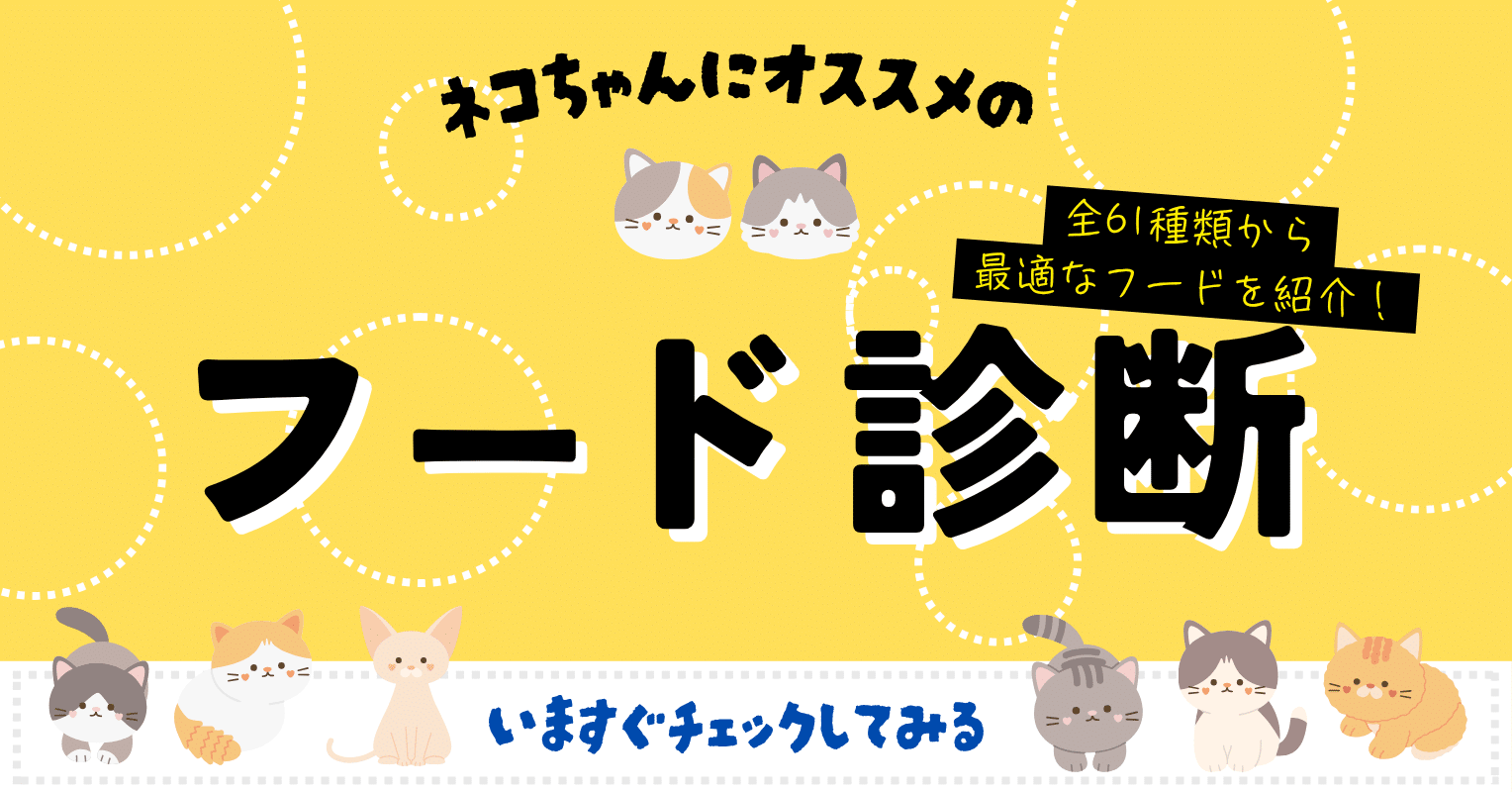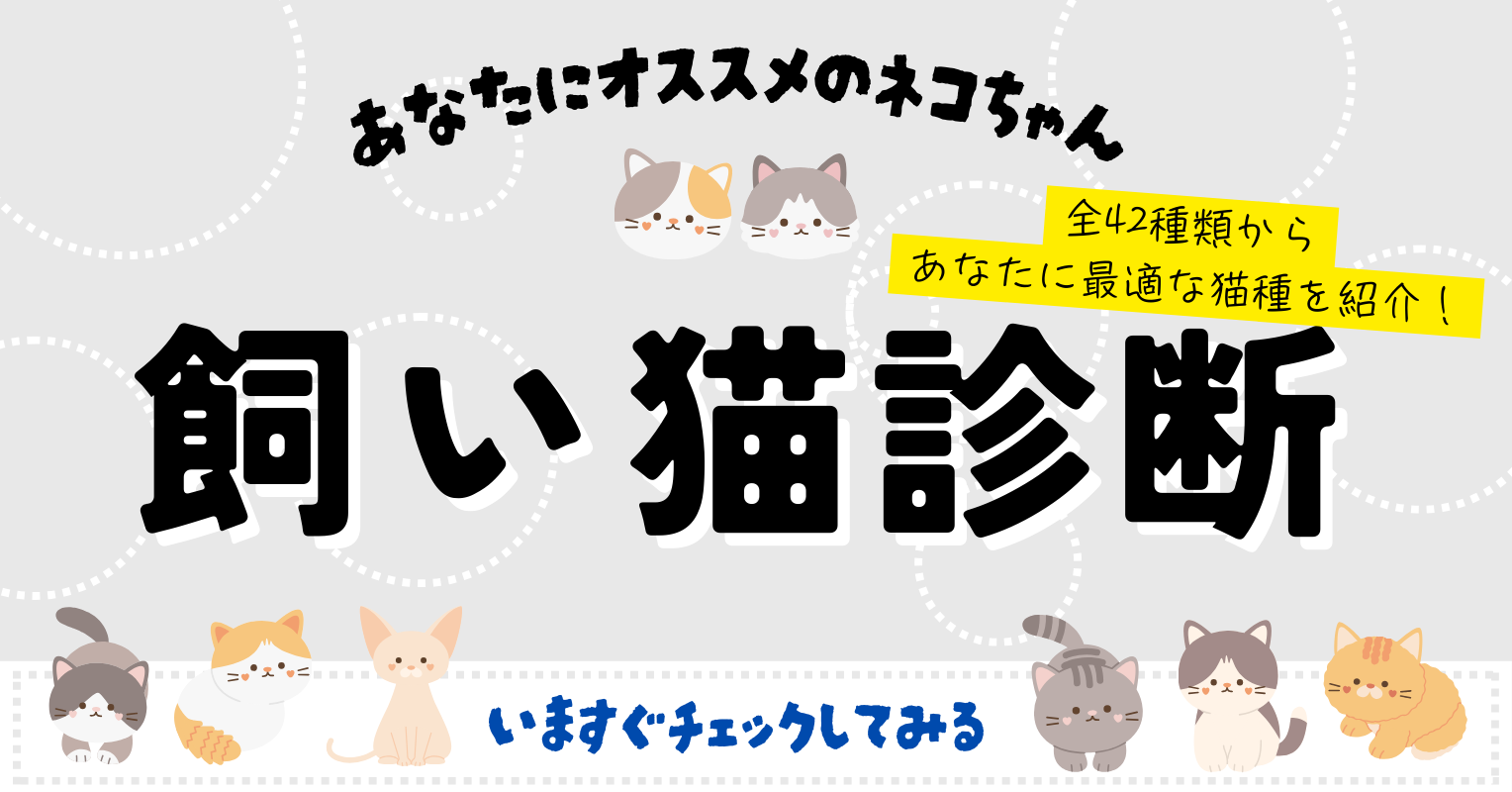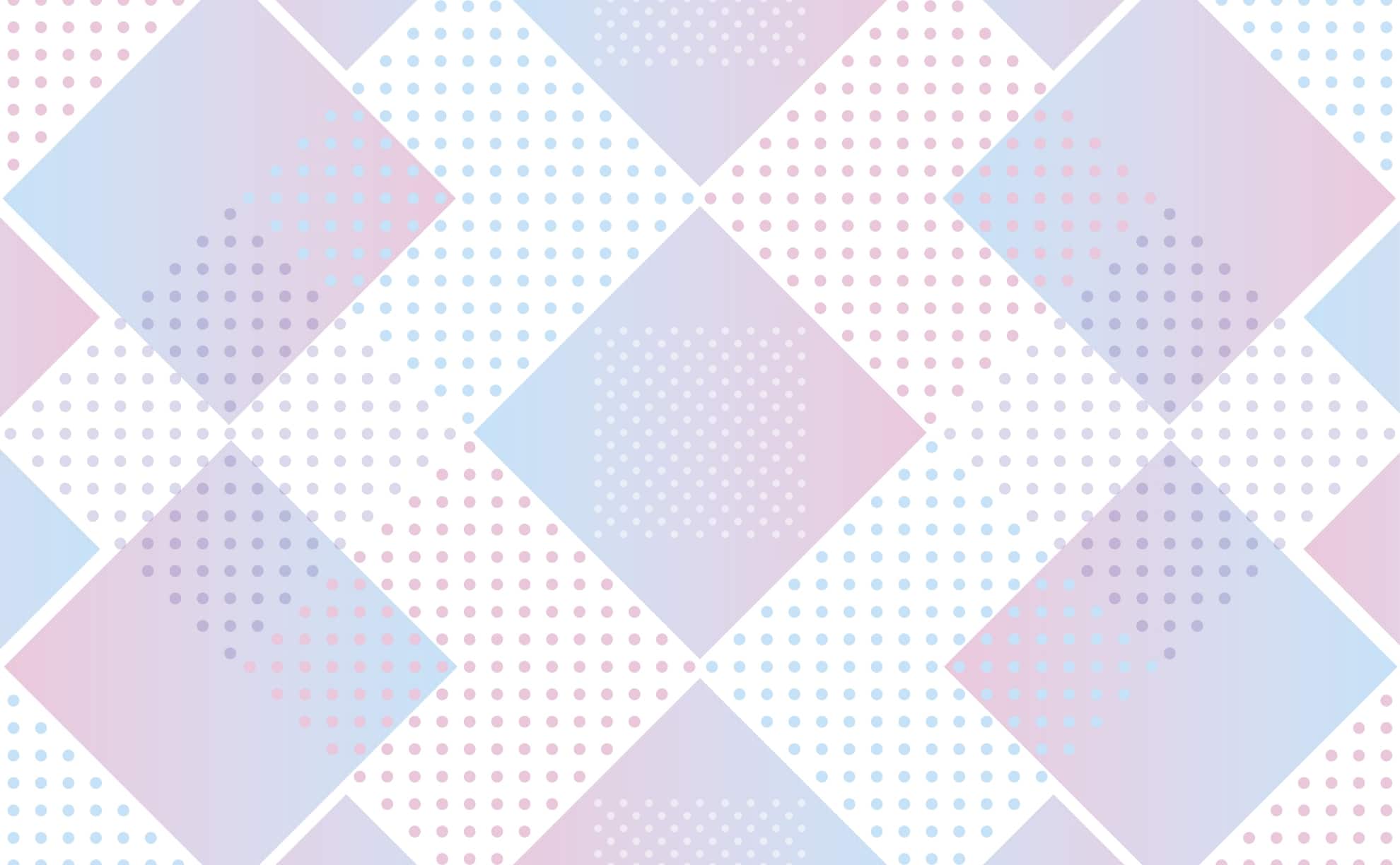「アオーン…」という愛猫の夜鳴きで、ぐっすり眠れない夜が続いている…そんな悩みを抱えていませんか?
猫の夜鳴きには、単純な空腹から病気のサインまで、さまざまな原因があります。
でも大丈夫。食事の工夫で改善できることが多いんです。
この記事では、夜鳴きの原因を見つけて、食事を中心とした対策方法をわかりやすく解説します。
- 夜鳴きの3つの原因と、家庭でできるチェック方法
- 食事の時間や回数を変えるだけでできる4つの対策
- 満腹感が続くフードの選び方とおすすめ商品
- 老猫の認知症や甲状腺の病気への対応方法
- 危険な症状の見分け方と病院に行くタイミング
猫の夜鳴きは食事で改善できる?原因から考えよう

猫の夜鳴きは、飼い主さんにとって本当につらい悩みですよね。
でも、なぜ鳴いているのか原因がわかれば、対策も見えてきます。まずは、夜鳴きの原因を3つのタイプに分けて考えてみましょう。
猫の夜鳴きの原因は大きく3つに分けられる
猫の夜鳴きは「症状」のひとつです。その原因は大きく3つのタイプに分けることができます。
- 生理的な欲求
- 環境や行動の問題
- 病気が原因
- ①. 生理的な欲求(お腹がすいた、のどが渇いたなど)
-
最も多いのが、お腹がすいて鳴くケースです。猫は本来、明け方や夕暮れに活発になる動物。早朝4時~6時頃に「ごはんちょうだい!」と鳴くのは、ある意味自然な行動なんです。
また、水が汚れていたり、トイレが汚いときも鳴いて訴えることがあります。猫はきれい好きな動物なので、不快な環境にはストレスを感じてしまいます。
- ②. 環境や行動の問題(ストレス、退屈、甘えなど)
-
引っ越しや新しいペットが来たなど、環境の変化はストレスの大きな原因になります。また、日中の遊びが足りないと、夜中に余ったエネルギーを発散しようとして鳴くこともあります。
そして見逃せないのが「学習した鳴き」です。
鳴けば飼い主さんが起きてごはんをくれる、遊んでくれる…そんな経験を重ねると、猫は「鳴けばいいことがある」と学習してしまいます。
- ③. 病気が原因(特に10歳以上の老猫は要注意)
-
10歳を超えた老猫の場合、病気が原因で鳴いている可能性があります。
特に多いのが:
- 甲状腺の病気(甲状腺機能亢進症)
- 認知症(認知機能不全症候群)
- 関節の痛みなど
これらの病気は、症状が重なることも多く、判断が難しいので注意が必要です。
💭 著者の経験談

我が家の愛猫も3歳頃から夜鳴きが始まりました。最初は甘えかと思っていましたが、食事の時間を寝る前に変えただけで、びっくりするほど改善されました。猫も人間と同じで、お腹が空くと眠れなくなるんですね。
夜鳴きの原因セルフチェックリスト

愛猫の夜鳴きの原因を探るため、以下の項目をチェックしてみましょう。
猫の基本情報
- 年齢は何歳?避妊・去勢手術は済んでいる?
- 最近、体重が増えた?減った?
- 食欲や水を飲む量、うんちやおしっこに変化はない?
生活環境のチェック
- 最近3ヶ月以内に引っ越しした?新しい家族やペットが増えた?
- トイレはきれい?場所は使いやすい?
- 水飲み場は猫が飲みやすい場所にある?
生活習慣のチェック
- 日中、どれくらい遊んであげている?
- 寝る前に遊ぶ時間はある?
- ごはんの時間は何時?毎日同じ?
鳴き方の特徴
- 飼い主さんに向かって鳴く?それとも、どこか不安そうに鳴く?
- 特に早朝(4時~6時頃)に集中して鳴く?
猫の夜鳴きを食事で改善する4つの方法

猫の夜鳴きが早朝の空腹によるものなら、食事の工夫で大きく改善できます。大切なのは「いつ」「どのように」ごはんをあげるかです。
1. 寝る前にごはんをあげて満腹にする
一番簡単で効果的な方法は、飼い主さんが寝る直前(夜10時~11時頃)にごはんをあげることです。夜中から朝までの空腹時間を短くすることで、早朝の「お腹すいた!」という鳴き声を防げます。
多くの猫で効果が見られます。
2. 食事の回数を増やして空腹を防ぐ
1日2回の食事を、1日3~4回に小分けする方法もおすすめです。食事の間隔を短くすることで、強い空腹感を感じにくくなります。特に最後の食事を寝る前にすると、より効果的です。
3. 「遊び→ごはん→寝る」のリズムを作る
猫の自然な行動パターンを活用した方法です。
寝る前に15~20分しっかり遊んで、その直後に少しごはんをあげます。これは猫の「狩り→食事→毛づくろい→睡眠」という本能的な流れに合っているので、満足して眠ってくれやすくなります。
💭 飼い主Tさんの体験談
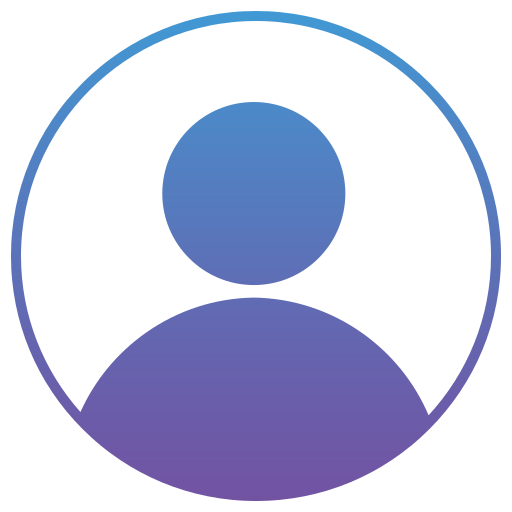
「毎晩9時に15分間、猫じゃらしで思いっきり遊んでから、少しウェットフードをあげるようにしました。1週間ほどで夜鳴きがほとんどなくなり、朝6時まで静かに寝てくれるようになりました。」
4. フードそのものを見直す
食事時間の調整でも改善しない場合は、フード自体を見直してみましょう。満腹感が長く続く成分や、リラックスできる成分が入ったフードを選ぶことで、問題が解決することもあります。
夜鳴き対策フードの選び方:満腹感と消化の良さがポイント

夜鳴き対策としてフードを選ぶときは、「満腹感が続く」「消化が良い」「気持ちを落ち着かせる」という3つのポイントに注目しましょう。
満腹感を長持ちさせる成分
満腹感のカギとなるのが「食物繊維」です。
サイリウムやビートパルプといった食物繊維は、お腹の中で水分を吸って膨らみ、長く留まることで、猫が満腹感を感じやすくなります。
気持ちを落ち着かせる成分
最近注目されているのが「L-トリプトファン」という成分です。
これは「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの材料となるアミノ酸で、猫の不安を和らげ、リラックスさせる効果が期待できます。
消化の良さも大切
いくら良い成分が入っていても、消化できなければ意味がありません。高品質なタンパク質を使った、消化率の高いフードを選びましょう。
夜鳴き対策におすすめのフード

- 製品名:AllWell 室内猫用(贅沢素材入りフィッシュ味天然小魚とささみフリーズドライ入り)
- 主な特徴:食物繊維、GABA配合
- 期待できる効果:満腹感キープ、リラックス効果
- おすすめの猫:室内飼いの成猫

- 製品名:ヒルズ サイエンス・ダイエット 室内猫の毛玉・体重ケア アダルト 1~6歳 成猫用 チキン
- 主な特徴:高繊維、低カロリー、L-カルニチン配合
- 期待できる効果:体重管理、毛玉ケア
- おすすめの猫:室内飼いで体重が気になる猫
自動給餌器で夜鳴きは改善する?選び方とおすすめ機種

早朝の空腹による夜鳴きには、自動給餌器がとても効果的です。決まった時間に自動でごはんが出るので、飼い主さんが早起きする必要もなくなります。
でも、自動給餌器の本当の価値はそれだけではありません。最も重要なのは、「鳴けば飼い主さんが起きてごはんをくれる」という猫の学習パターンを断ち切れることです。
猫は「機械からごはんが出る」ことを学習するので、飼い主さんに向かって鳴くことが減っていきます。
自動給餌器を選ぶときのポイント
- 時間と量を正確に設定できる:1日に何回も、5g程度の少量から設定できるもの
- いたずら防止機能:賢い猫が開けられないよう、しっかりロックできるもの
- 電源の種類:停電でも安心なように、コンセントと電池の両方使えるもの
- お手入れのしやすさ:タンクや受け皿が取り外して洗えるもの
💭 著者の経験談

カメラ付きのモデルなら、外出先から愛猫の様子を確認できて安心です。最近はマイク機能で声をかけられる製品もありますよ!
人気の自動給餌器比較

- 製品名:うちのこエレクトリック カリカリマシーンV2C/スマホ連動型自動給餌器
- 主な機能:高画質暗視カメラ、スマホ連携、音声録音
- いたずら防止:スライドロック式の蓋、盗み食い防止構造
- ユーザーの評価:夜鳴き対策に効果的と評判、アプリも使いやすい

- 製品名:PETKIT YUMSHARE SOLO with Smart Pet Feeder(P571)
- 主な機能:高画質カメラ、静音設計(65.6dB)
- いたずら防止:固定ロック、重さで転倒防止
- ユーザーの評価:静かで防犯性も高いバランス良好モデル

- 製品名:Wansview 3MPネットワークカメラ付き自動給餌器P1
- 主な機能:2K高精細カメラ、Alexa対応、会話機能
- いたずら防止:密閉性の高い蓋
- ユーザーの評価:映像がきれいで家族で共有できると好評
食事以外の夜鳴き対策:遊びと環境づくりでストレス解消
食事の工夫と一緒に、猫のストレスを減らして、エネルギーを発散させることも大切です。猫が心も体も満足した状態で夜を迎えられるよう、生活環境を見直してみましょう。
寝る前の遊びが一番大切

最も重要なのは、飼い主さんと一緒に遊ぶ時間です。特に寝る前の15~20分間、猫じゃらしなどで本気で遊んであげると、適度に疲れて深く眠りやすくなります。
猫が安心できる環境づくり

- 高い場所を作る:キャットタワーや棚で、猫が上から見渡せる場所を作る
- 隠れ家を用意:段ボール箱やドーム型ベッドなど、一人になれる場所を作る
- 一人遊びできるおもちゃ:パズルフィーダーや電動おもちゃで、飼い主さんがいない時も退屈しない工夫
- 快適な寝床:静かで安心できる場所に、ふかふかのベッドを用意。飼い主さんの匂いがついたブランケットを置くとより安心します
💭 著者の経験談

これらの工夫で、猫のストレスレベルが全体的に下がり、夜鳴きしにくい穏やかな状態を保てるようになります。ぜひ試してみてくださいね。
老猫・病気の猫の夜鳴きと食事管理

10歳を超えた老猫の夜鳴きには、若い猫とは違う病気が隠れている可能性があります。特に注意が必要な病気と、その食事管理について説明します。
老猫の夜鳴きは認知症や甲状腺の病気のサイン?
以前は静かだった老猫が、突然理由もなく大声で鳴き続けるようになったら、病気のサインかもしれません。老猫の夜鳴きの3大原因は以下の通りです。
- 甲状腺機能亢進症:甲状腺ホルモンが出すぎる病気。常に落ち着きがなくなり、食欲が増すのに痩せていく、水をたくさん飲むなどの症状が出ます
- 認知症(認知機能不全症候群):人間の認知症と似た症状。場所がわからなくなる、昼夜逆転、トイレの失敗などが特徴です
- 慢性的な痛み:関節症や歯周病による痛み。夜間に痛みが強く感じられて鳴くことがあります
甲状腺機能亢進症の猫の食事:ヨウ素制限食
甲状腺機能亢進症と診断されたら、食事療法という選択肢があります。甲状腺ホルモンの材料となる「ヨウ素」を制限した療法食を与える方法です。
代表的なのが、ヒルズの「y/d」という療法食。このフードだけを与えることで、多くの場合3週間以内に症状が改善すると報告されています。

〈猫用〉y/d ワイディー ドライ
ただし、この療法食を成功させるには「絶対にこのフードだけ」という徹底管理が必要です。おやつや他のフード、人間の食べ物は一切ダメ。多頭飼いの家庭では管理が難しいこともあります。
認知症の猫の食事:脳の健康をサポートする栄養
猫の認知症は完治しませんが、食事で症状の進行を遅らせることができます。脳の健康をサポートする栄養素を積極的に摂りましょう。
- 抗酸化物質(ビタミンE、C):脳の老化を防ぐ
- オメガ3脂肪酸(DHA、EPA):脳の健康維持に必要。魚油に多く含まれます
- B群ビタミン、L-カルニチン:脳のエネルギー代謝をサポート
💭 著者の経験談

最近は「腸内環境が脳の健康に影響する」という考え方も注目されています。善玉菌(プロバイオティクス)も、不安を和らげる可能性があると言われていますよ。
夜鳴きに効くサプリメント:正しい選び方
夜鳴きの原因が不安やストレスの場合、リラックス効果が期待できるサプリメントを試してみる価値があります。医薬品ではないので効果には個体差がありますが、猫の生活の質を向上させる可能性があります。
| 有効成分 | どんな働き? | 研究データ | おすすめの状況 |
|---|---|---|---|
| α-カソゼピン(ジルケーン) | 牛乳由来の成分で穏やかに気持ちを落ち着かせる | 研究論文あり | 環境変化によるストレス |
| L-テアニン | 緑茶の成分でリラックス効果 | 研究データあり | 全般的な不安の軽減 |
| L-トリプトファン | セロトニンの材料で気分を安定させる | 研究データあり | ストレス関連の行動 |
| 猫用フェロモン(フェリウェイ) | 猫の頬から出る安心フェロモンの合成品 | 研究データあり | 環境ストレス |
動物病院へ行くべき夜鳴きの見分け方

猫は不調を隠すのがとても上手な動物です。夜鳴きが単なる行動の問題か、深刻な病気の初期症状かを見極めることが大切です。
最も注意すべきは「以前は静かだった猫が突然鳴き始めた」ケースです。これは体の中で何か異変が起きている重要なサインです。
危険な症状リスト:こんな症状があったらすぐ病院へ

以下の症状が一つでもあったら、すぐに動物病院へ連れて行きましょう。
食事や排泄の異常
- 食欲が急に増えた、または減った
- 水をがぶがぶ飲む(1日に体重1kgあたり50ml以上)
- 食欲はあるのに痩せていく
- 嘔吐や下痢が続く
行動の異常
- おしっこが出ない、血尿が出る、トイレ以外で粗相する
- 元気がない、ふらつく、隠れて出てこない
- 急に攻撃的になった
緊急性の高い症状
- 口を開けてハァハァ呼吸する(開口呼吸)
- 安静時でも呼吸が速い(1分間に40回以上)
- 触ると痛がる、足を引きずる
これらは猫からの重要なSOSサインです。早めに見つけて治療することで、愛猫の健康を守ることができます。個体差があります。獣医師にご相談ください。(公益社団法人日本獣医師会)
よくある質問(FAQ)
まとめ:猫の夜鳴きは正しい対策で改善できる
愛猫の夜鳴きに対しては、原因に応じた段階的な対策が解決への近道です。この記事で紹介した以下のポイントを実践してみてください。
- 原因を見つける:チェックリストで問題を整理
- 食事管理を工夫する:時間、回数、内容の3つを調整
- 満腹感が続くフードを選ぶ:食物繊維とリラックス成分を活用
- 環境を整える:ストレスを減らして活動量を確保
- 病気のサインを見逃さない:危険な症状があればすぐ病院へ
夜鳴きは愛猫からの大切なメッセージです。その声に耳を傾けて、適切に対応することで、猫も飼い主さんも安らかな夜を取り戻せます。猫には個体差がありますので必要なときは獣医師のアドバイスも活用しながら、愛猫との健やかな生活を目指してください。